今回は、出産後のママに向けて産後ケアとは何をするのか、助産師&自治体のサービスガイドについて解説します。
- 最近よく聞く産後ケアって何?
- 産後ケアはどんなサービスがあるの?
- 産後ケアにおける自治体と民間の違いを知りたい
「赤ちゃんが生まれたら、どんなサポートが受けられるの?」 「産後、ちゃんと過ごせるかな…」
そんな不安を抱えているママも多いのではないでしょうか。
実は、出産後のママと赤ちゃんをサポートする「産後ケア」というサービスがあります。
 サキココ
サキココ授乳指導や育児相談、心身の回復に必要な休養まで、さまざまなサポートを受けられるよ!
現代日本では、核家族化や共働きの増加で産後の家族サポートを得にくく、高齢出産や産後うつの増加も相まって、育児負担が深刻化しています。



こうした背景から、産後ケアの重要性が注目されているよ!
産後ケアは自治体が提供するサービスもあれば、より手厚いケアを受けられる民間の施設もあります。
でも、どんなサービスを選べばいいのか、費用はどのくらいかかるのか、知りたいことがたくさんありますよね。
この記事では、産後ケアの基本から、自治体と民間それぞれのサービスの特徴、上手な選び方まで、詳しくご紹介します。
産後ケアとは?


「産後ケアって何?」「どのようなサポートが受けられるの?」と産後ケアについて気になっているママも多いと思います。
出産後のママが慣れない育児で疲れやすくなる中、育児や心身のケアを通じてママを支えるサービス
出産後のママと赤ちゃんの心身の健康を支える産後ケアは、安心して子育てを始めるために重要なサポートです。
産後は身体の回復期であると同時に、育児技術の習得や心理的な不安も大きい時期。



そんなデリケートな時期を助産師や看護師、医療スタッフと共に乗り越えましょう。
また、産後うつは10人に1人が経験すると言われており、早期発見・対応が大切と言われています。
産後うつについてはこちらの記事を確認してください。


さらに、核家族化が進み、身近に育児の相談相手がいないママも増えています。
産後ケアでは、授乳指導、育児相談、ママの休養サポートなど、専門家による総合的なケアを受けられます。



自治体によっては、利用条件や予約状況も変化するので事前に確認することをおすすめするよ◎
早めに利用を検討することで、より充実した子育てのスタートを切れることでしょう。
産後ケアには、主に以下の3つの形態があります。
訪問型産後ケア
助産師や看護師が自宅を訪問し、授乳指導や育児相談、体のケアを行う。



自宅に来てくれるから、移動がなくてとっても楽♪
ショートステイ型
産後間もないママは赤ちゃんと一緒に施設に泊まり、専門スタッフからサポートを受けながら休息できるサービス。



主に休息を目的として産後ケアを利用するママが多いよ!
デイケア型
日中のみ施設を利用し、授乳指導や産後の体調管理のアドバイスを受けられる。
お昼ご飯を提供してくれる施設も多く、手ぶらで気軽に利用できるところもあります。



食事を作らなくてよいだけでも、体も心も休めるよね。
最近では、自治体のウェブサイトからオンラインで申し込めるところも増えています。



出産前に登録をしておくとスムーズに利用できる場合もあるので、事前に確認してね。
産後ケアのサポート内容


産後のママは、赤ちゃんのお世話に追われる中で、心身の疲れを感じやすいものです。



そんなときに役立つのが「産後ケア」
授乳や育児の悩みを相談できたり、休息をとれたりすることで、ママの負担を軽減し、赤ちゃんとの生活をより穏やかに過ごせるようサポートします。
ここでは、産後ケアの具体的な内容で実際に利用目的で多い「授乳サポート」「休息」「育児相談」の3つのポイントについて詳しく見ていきましょう。
授乳相談
授乳は赤ちゃんにとって大切な時間ですが、母乳がうまく出ない、赤ちゃんが飲んでくれないなど悩むママも多いです。
産後ケアでは、助産師が母乳の状況を確認し、ママの悩みに合った適切なアドバイスをしたり、授乳の姿勢やミルクの与え方を説明したりしてくれます。
うまく飲めない場合や乳房のトラブルへの対応、ミルクとの併用方法も相談できるため、ママと赤ちゃんに合った授乳方法を見つけることができます。



一人ひとりに合ったアドバイスができるから、ママの不安も解消できるよ!
退院後に母乳トラブルで悩んでいるママはこの記事も確認してみてください。
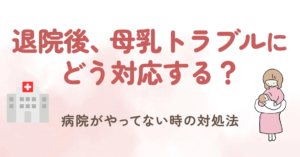
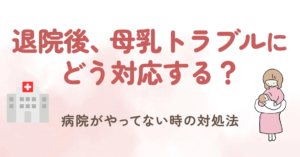
休息
産後のママにとって、十分な休息をとることはとても大切です。
しかし、赤ちゃんのお世話で夜間の授乳や寝不足が続き、ゆっくり休む時間が取れないことも。
睡眠不足は心身の疲労を引き起こし、産後うつのリスクを高めることも。



大切な時期だからこそ、一人で抱え込まず頼ってほしい。
産後うつについての記事はこちらからチェックしてね。


産後ケアでは、助産師やスタッフが赤ちゃんを一時的に預かってくれる施設もあり、ママが安心して休める環境が整っています。
心身をしっかり回復させることで、育児の負担を軽減し、赤ちゃんとの時間をより穏やかに過ごせるようサポートしてくれます。
育児相談
初めての育児はわからないことだらけ。
赤ちゃんの泣き方や寝ぐずり、発育のことなど、小さな悩みでも気軽に相談できるのが産後ケアの魅力です。
助産師を含め専門スタッフがママの不安に寄り添い、的確なアドバイスをくれるので、安心して育児に向き合えます。



他のママとの交流の場がある施設もあり、一人で抱え込まずに育児ができる環境が整っているよ◎
自治体と民間の産後ケアの違い
-1.jpg)
-1.jpg)
産後ケアには、自治体が提供するサービスと、民間施設が運営するサービスの2種類があります。



自治体と民間の違いがよく分からないというママもいるよね!
自治体の産後ケアは比較的低価格で利用できる一方、民間施設では料金は高めではありますがより充実したケアを受けられることも。
自分に合った産後ケアを選ぶために、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
自治体の産後ケア
最近では、自治体が提供する産後ケアサービスも充実しています。
多くの自治体では、出産後4ヶ月以内の母子を対象に、様々なサービスを提供しています。
利用するにあたり、注意点があります。



自治体のサービスは利用条件や予約状況により、希望通りに利用できない場合もあるよ!
主なサービス内容は産後ケアのサポート内容で解説しています。
民間の産後ケア
民間の産後ケアサービスは、自治体のサービスに比べて料金は高めですが、より柔軟で手厚いケアを受けられます。



ラグジュアリーなホテルのような内装の施設も多く、産後のご褒美で利用したというママも♪
料金は高めですが、24時間体制の専門スタッフによるケアや個室での快適な環境、食事の充実など、サービスも充実しています。
例えば、都内の産後ケア施設では、次のようなサービスがあります。
- 24時間体制の助産師・看護師によるケア
- 赤ちゃんの夜泣き対応
- 産後の体のケア(ヨガ、エステ、マッサージなど)
- 栄養バランスの取れた食事提供
- 育児技術の個別指導
などが提供されています。
特に、実家のサポートが得られにくい方や、しっかりと休養を取りたい方には、民間施設の利用をおすすめします。
産後ケアの選び方
産後ケア施設を選ぶ際は、自治体と民間の違いを理解し、自分の状況や希望に合ったサービスを選ぶことが大切です。
選び方のポイントは次の通りです。
- 費用と補助の有無
- 自身の状況(体調・家族のサポート体制)の確認
- 居住地域で利用できるサービスの確認
- サービス内容(休養・授乳指導・育児相談など)
- 施設の雰囲気や設備
- 宿泊・通所の違い
- 利用しやすさ
産後ケア施設を選ぶ際は、費用や自治体の補助を確認し、希望するサポート内容があるかをチェックしましょう。



宿泊型か通所型かも重要なポイントだよ!
さらに、施設の雰囲気や設備、アクセスの良さ、予約の取りやすさを考慮すると、より自分に合った安心できる産後ケアを見つけやすくなります。



無理なく心身を休めるためにも、自分の状況に合わせて選んでみてね。
まとめ


今回は、産後ケアって何するの?助産師&自治体のサービスガイドについて解説しました。
産後ケアは、授乳サポートや休息、育児相談など、出産後のママを支える大切なサービスです。



十分な休息や相談できる環境があると、心身の負担も軽くなるよね♡
一人で抱え込まず、頼れる制度は積極的に活用しましょう。
ママの心と体を大切にしながら、無理せず育児ができる環境を整えてくださいね。
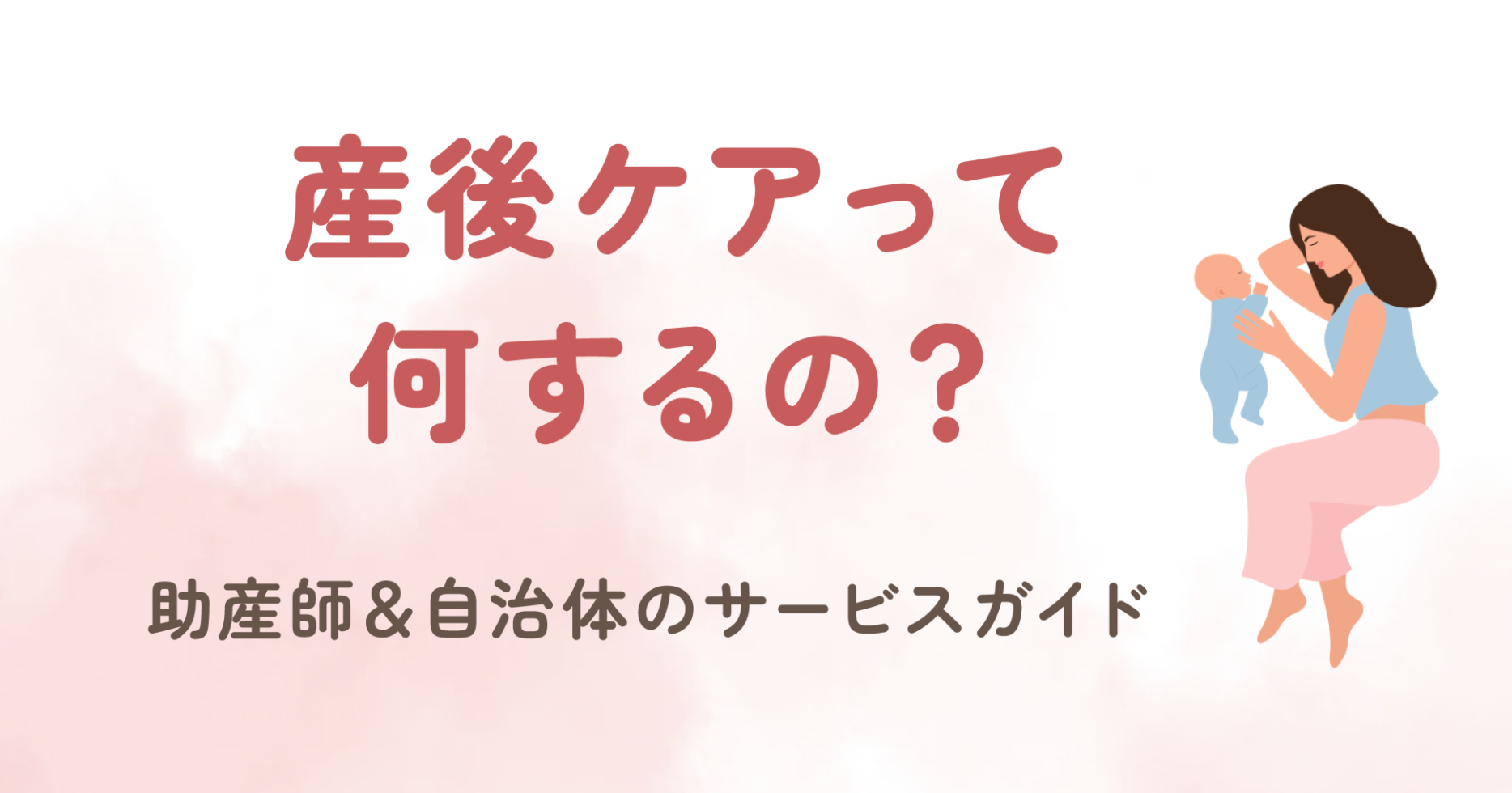
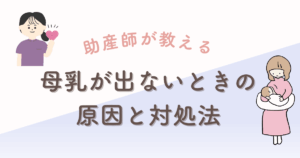
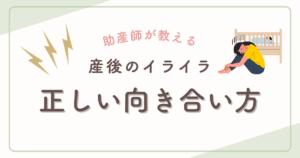
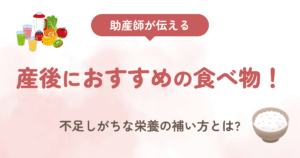
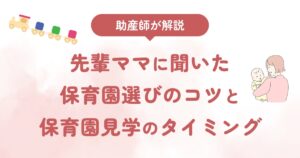
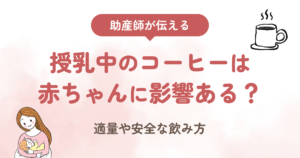
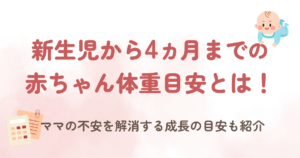
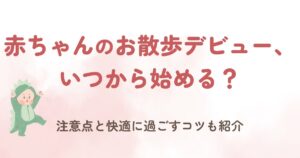
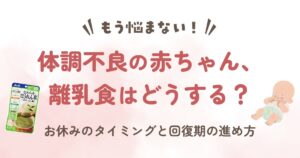
コメント