今回は、助産師として多くの赤ちゃんとママ達をサポートしてきた私が、赤ちゃんが見せる「眠いサイン」と、寝かしつけのコツを分かりやすく解説します。
- 赤ちゃんの「眠いサイン」って何?
- 寝かしつけのコツを知りたい
- 寝かしつけアイテムを教えて欲しい。
赤ちゃんの寝かしつけに悩むママやパパは多いですよね。
「なかなか寝てくれない」「寝かしつけに何時間もかかる」とお悩みですが、その解決の鍵は赤ちゃんの眠いサインを理解すること。
 サキココ
サキココ赤ちゃんが泣き出す前に示す小さなサインに気づけば、スムーズな寝かしつけが可能になるよ!
赤ちゃんの体内時計に合わせた適切なタイミングで寝かしつければ、赤ちゃんもぐっすり眠れて、ママやパパの負担も軽減できますよ。
今回は、助産師の視点から赤ちゃんの「眠いサイン」と、スムーズに寝かしつけるコツをご紹介します。
赤ちゃんが出す「眠いサイン」


赤ちゃんの「眠いサイン」ってどんなものがあるの?「眠いサイン」を見逃すとどうなるの?と心配になるママやパパもいますよね。



言葉で「眠い」と伝えられないから、眠くなると特有のサインを出すよ!
このサインに気づいて適切なタイミングで寝かしつけをすることで、赤ちゃんはスムーズに眠りにつけます。
代表的な「眠いサイン」と、それを見逃すとどうなるのかについて説明していきます。
月齢別「眠いサイン」
月齢によっても違いがありますが、代表的なものをチェックしましょう。



これらのサインが出たら、眠る準備を始める合図です。
- 目をこする
- あくびをする
- まばたきが増える
- 手足をバタバタさせる
- 顔をこすりつける
- ぐずり始める
- 目がうつろになる
- 声のトーンが変わる
- 遊びに集中できなくなる
- 何かにつかまって甘える
- ぼんやりしてくる
- いらいらして怒りっぽくなる
赤ちゃんによって眠いサインの出方は異なるため、日頃から赤ちゃんの様子を観察し、どのようなサインが現れるのかを知っておくことが大切です。



見極めが難しいけど、サインに気づければ寝かしつけが楽になるかも!
眠いサインを見逃すとどうなる?
赤ちゃんの眠いサインを見逃してしまうと、適切なタイミングで寝かしつけができず、結果的に寝つきが悪くなることがあります。
これは、赤ちゃんが「眠いのに寝られない」という状態になり、興奮してしまうためです。
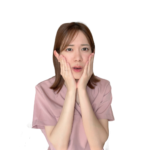
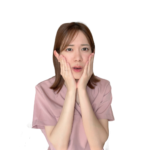
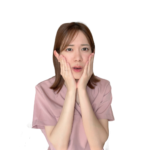
眠気がピークを過ぎてしまうと、以下のような状況になることも!
- 寝ぐずりがひどくなる
- 夜泣きが増える
- 寝かしつけに時間がかかる
- 生活リズムが乱れる
赤ちゃんがスムーズに眠れるようにするためには、眠いサインを見逃さずに、適切なタイミングで寝かしつけすることが大切です。
眠そうな様子が見えたら、静かで落ち着いた環境を作り、スムーズに眠れるようサポートしてあげましょう。



この記事で詳しく書いてあるよ♪
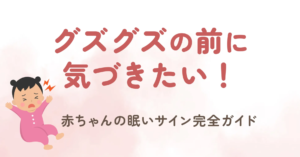
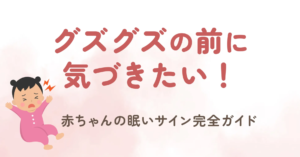
赤ちゃんの眠りのメカニズムを理解しよう


「赤ちゃんがなかなか寝つかない」「やっと寝たと思ったらすぐ起きてしまう…」そんな悩みを抱えるママやパパは多いですよね。
でも、赤ちゃんの眠りには大人とは違うリズムがあり、それを知ることで対応しやすくなります。
助産師として多くの赤ちゃんを見てきた経験から言えるのは、「赤ちゃんの眠りの仕組みを知ることが、寝かしつけの第一歩」ということ。



ここでは、赤ちゃんの睡眠の特徴を詳しく解説していきます!
赤ちゃんの睡眠サイクルは大人と違う
大人の睡眠は、浅い眠り(レム睡眠)と深い眠り(ノンレム睡眠)を90分ごとに繰り返します。



そのため、眠りが浅く、ちょっとした刺激で目を覚ましやすいからすぐ起きてしまうことも。
助産師として、ママやパパから『抱っこしてやっと寝たのに、布団に置くとすぐ起きる』という相談をよく受けます。
これは、赤ちゃんがまだ深い眠りに入っていないタイミングで布団に置かれてしまうからなんです。
月齢ごとの睡眠の変化
赤ちゃんの眠り方は、月齢によっても変化していきます。
新生児期(0〜1ヶ月)
助産師の立場から見ると、この時期の赤ちゃんは昼夜の区別がなく、1日16〜20時間ほど眠るのが普通。
でも、一度に長く眠ることは少なく、2〜3時間おきに目を覚まして授乳が必要になります。
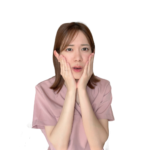
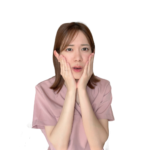
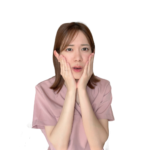
オムツ交換して、授乳して・・・あっという間に次の授乳時間!
生後2〜3ヶ月
少しずつ昼夜のリズムができ始め、夜にまとまって寝る赤ちゃんも増えてきます。
赤ちゃんも大人と同じように、メラトニンという睡眠ホルモンの分泌によって眠りに誘われます。
睡眠や覚醒のリズムを調節するホルモンのこと
ただし、まだ睡眠サイクルが短く、浅い眠りが多いので、ちょっとした刺激で目が覚めることも。
生後3ヶ月頃からメラトニンが分泌し始め、昼と夜の区別がつくようになると言われています。



この時期から、昼夜のリズムを整えることが重要になるよ!
生後4〜6ヶ月
夜にまとまって眠る赤ちゃんが増える時期。
ただし、この頃に「睡眠退行」と呼ばれる現象が起こり、今までよく寝ていた赤ちゃんが急に夜泣きしやすくなることも。
赤ちゃんの睡眠リズムが整っていたのに突然乱れる現象
助産師としては、「赤ちゃんの成長の一環」と考え、焦らず見守ることをおすすめしています。
覚醒時間を理解する
「寝かしつけを頑張っているのに、なかなかうまくいかない…」と悩むママやパパも多いですが、まずは赤ちゃんの眠りの仕組みを理解することが大切です。
赤ちゃんが快適に過ごせる覚醒時間(起きている時間)は月齢によって異なります。
- 新生児〜1ヶ月: 45〜60分
- 2〜3ヶ月: 1〜1.5時間
- 4〜6ヶ月: 1.5〜2.5時間
- 7〜12ヶ月: 2.5〜3.5時間
この覚醒時間を超えると、赤ちゃんは疲れすぎて逆に寝付きが悪くなることがあります。



覚醒時間も考慮して寝かしつけのタイミングを計ってみよう!
赤ちゃんの活動限界時間についてはこの記事をチェックしてくださいね。
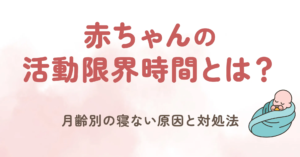
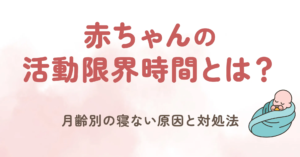
助産師の視点での寝かしつけのコツについては、次の章で詳しく解説するので、ぜひ実践してみてくださいね!
助産師が教える効果的な寝かしつけのコツ


赤ちゃんの寝かしつけに苦労しているママ・パパは多いのではないでしょうか?
「抱っこしないと寝ない」「寝てもすぐに起きてしまう」など、赤ちゃんの睡眠に関する悩みは尽きません。
助産師の視点から、赤ちゃんが心地よく眠れる寝かしつけのコツを詳しく解説します。



眠いサインを見つけたら、次に紹介する適切な寝かしつけの方法を実践してみてね♪
環境を整える
赤ちゃんが安心して眠れる環境づくりが重要です。
特に新生児期の赤ちゃんは刺激に敏感なので、テレビやスマホの光を避け、落ち着いた空間を整えましょう。



この記事で詳しく解説しているよ!
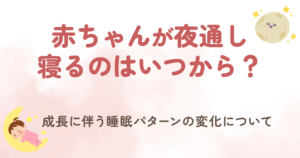
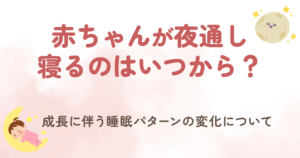
また、室温や湿度を調整し、快適な寝室をつくることも大切です。
\これ一つで快適な環境が確認できる!/


寝る前のルーティンを決める
決まった流れを作ることで、赤ちゃんは「次は寝る時間だ」と理解しやすくなります。
例えば、お風呂の後に授乳やミルクを飲み、少し抱っこした後に布団へ…という一定の流れを作ると、安心して眠れるようになります。



寝る前の絵本や子守唄や、赤ちゃんとスキンシップをとって安心させてあげてね♡
先輩ママがおすすめする絵本は、この記事で紹介しています。
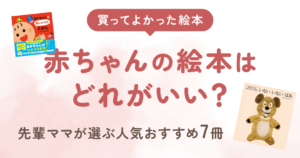
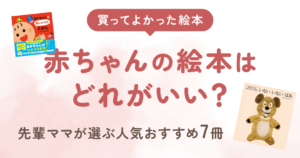
おくるみや寝具を工夫する
生後3ヶ月頃までは、おくるみで包んであげると安心しやすくなります。



モロー反射を防ぎ、赤ちゃんがぐっすり眠れる助けにもなるよ!
また、汗をかきやすい赤ちゃんのために、通気性の良い寝具を選ぶことも大切です。
季節に合った布団やパジャマを選び、赤ちゃんが快適に眠れる環境を整えましょう。



詳しくはこの記事をチェックしてね!
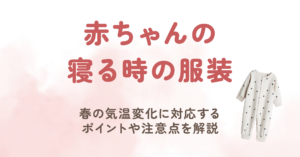
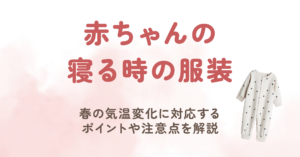
寝かしつけをラクにする便利アイテム3選


「なかなか寝てくれない…」「寝かしつけに時間がかかってクタクタ…」そんな悩みを抱えているママやパパへ。
助産師の視点から、赤ちゃんがぐっすり眠るために役立つ寝かしつけアイテムを3つ紹介します!
ホワイトノイズマシンで安心感アップ!
赤ちゃんはママのお腹の中で、常に「ゴーッ」という血流音や心音を聞いていました。



そのため、ホワイトノイズ(自然な雑音)を流すと安心して眠りやすくなると言われているよ!
おすすめは「Dreamegg D11 ホワイトノイズマシン 」
小型で持ち運びもでき、波の音や心音など複数の音を選べます。
\あのVOGUEで紹介された快眠グッズ!/



夜泣き対策にも◎
おくるみスリーパーでモロー反射を防ぐ!
赤ちゃんが突然ビクッとなる「モロー反射」で目を覚ましてしまうこと、ありませんか?
そんな時に便利なのが「エイデンアンドアネイ スワドル」。
\ふんわり包み込むことで、赤ちゃんが安心してぐっすり眠れるアイテム/



寝返り前の赤ちゃんにもぴったり!
多機能のぬいぐるみ ロボット登場!
赤ちゃんがリラックスできる環境作りも大切。
優しい光と音楽を流せる「多機能寝かしつけぬいぐるみ」は、寝る前の習慣として取り入れやすいアイテムです。
\機械を取り外して洗濯可能!衛生的でいつでも綺麗を保てる/
どれも助産師の視点からおすすめできるアイテムばかりです。



ぜひ、寝かしつけに取り入れてみてくださいね
まとめ


今回は、助産師として多くの赤ちゃんとママ・パパをサポートしてきた私が、赤ちゃんが見せる“眠いサイン”と、寝かしつけのコツを分かりやすく解説してきました。
眠いサインに気づいたら、すぐに寝る準備を始めることで、寝ぐずりや夜泣きを防ぎやすくなります。
また、寝る環境を整え、寝かしつけのルーティンを決めることで、赤ちゃんが安心して眠りにつく習慣を作ることができます。
毎日の育児は大変なことも多いですが、助産師としてお伝えしたいのは、無理をしすぎず赤ちゃんのペースに寄り添うことです。



赤ちゃんの眠いサインを見逃さず、上手に寝かしつけていきましょう!
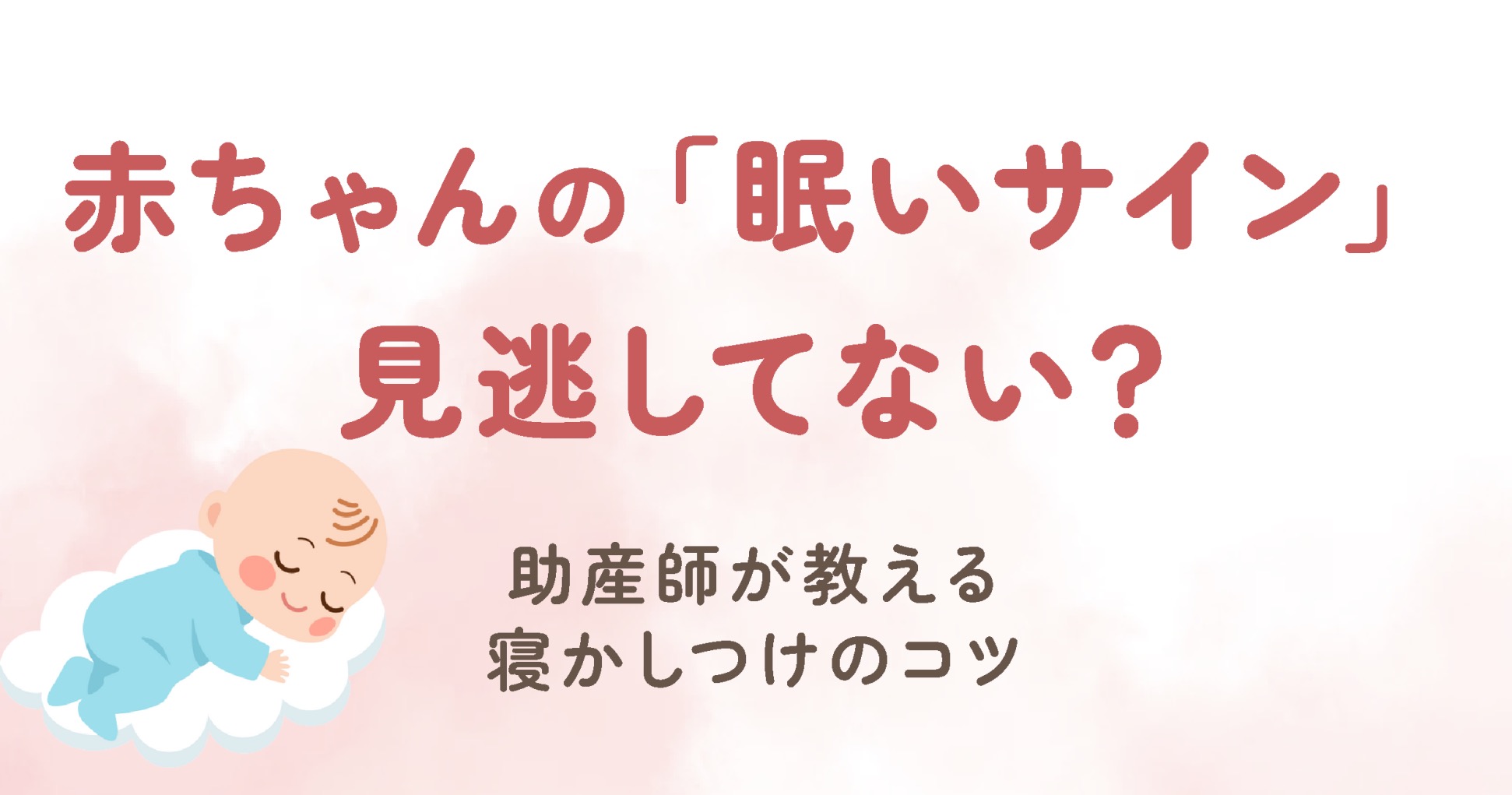



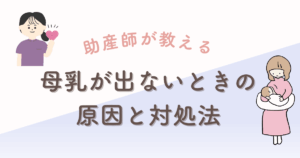
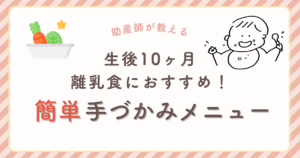
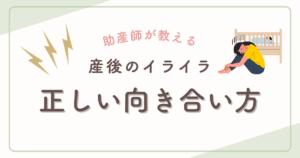
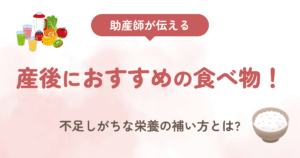
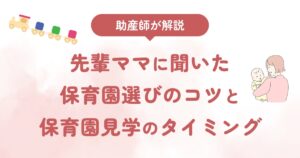
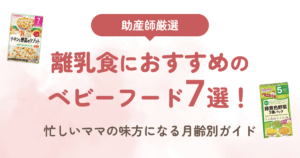
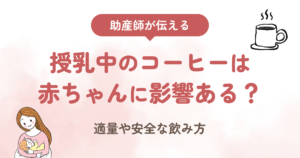
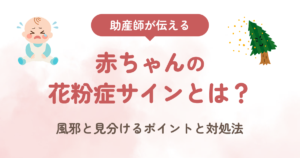
コメント